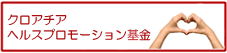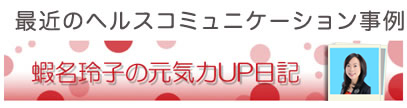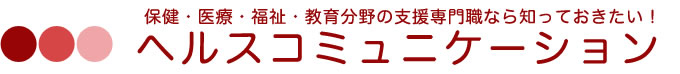
「ヘルスコミュニケーションとは、人々に、健康上の関心事についての情報を提供し、重要な健康問題を公的な議題に取り上げ続けるための主要戦略のこと」とWHO(世界保健機関)は定義づけています。
「健康についての正しい情報をただ伝えるのではなく、きちんと伝わるように戦略としての目線を持ちなさい」と言っているわけです。戦略を練るときのポイントが、アートと科学です。
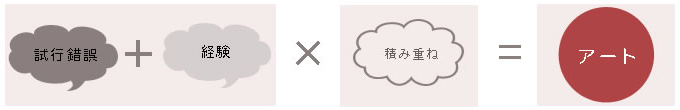
コミュニケーションがうまくいかないがための悩みを抱いた時、日本には、試行錯誤を繰り返して、解決の糸口を探っていこうとする経験重視型の支援専門職の方々が多いようです。とにかくたくさんの経験を積み、自分なりの方法を見出そうとする。こうした姿勢は、とても素晴らしいことです!
「この世でたったひとりしかいない、あなただからこそできるコミュニケーション術」は、相手のことを真摯に考え、役に立ちたいという心を込めて試行錯誤を繰り返し、そこから学び、創造力が鍛えられて初めて、生み出されるものだからです。人が感動するのは、そんなあなたの情熱が伝わったときです。これがヘルスコミュニケーションのアートの部分です。
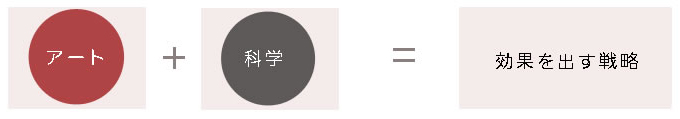
しかし、そういう経験重視型アプローチのみでは、コミュニケーションをとるのが苦手なあなた、まだ若くて経験のないあなた、経験したこともない難しいケースを抱えているあなたは、お手上げ状態になってしまいます。
そのようなとき、心理学や行動科学、社会科学などで使われている理論を応用すると、うまくいきやすくなります。
理論というのは、たくさんの人に調査をしたうえで「これなら、うまくいく」と立証されたものだからです。これがヘルスコミュニケーションの科学の部分です。アートと科学の目線をもって「いかに伝えるか」戦略を練る。これがヘルスコミュニケーションで大切なことなのです。
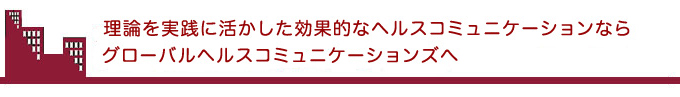
数多くの理論を理解し、それを現実のケースに応用できるようになるには、時間がかかります。また、理論や研究結果はカタイので、しっかり学ぼうとすると疲れます。日々の業務に追われている多忙な皆さまとしては、「ポイントをサッと覚えやすい形で知りたい」というのが本音でしょう。
弊社代表の蝦名(保健学博士)は、ヘルスコミュニケーションが生まれた1990年代、この学問の生みの国である米国のミシガン州立大学と大学院で、ヘルスコミュニケーションを学び(当時の指導教官だったキム・ウィッテイ博士は、米国疾病予防管理センター、CDC、のコンサルタントを兼任しておりヘルスコミュニケーションの先駆者のひとりです)、 弊社設立後は2004年から2007年にかけて財団法人日本公衆衛生協会の月刊誌『公衆衛生情報』にヘルスコミュニケーションについての連載を執筆し続ける等、日本におけるヘルスコミュニケーションの発展に寄与してきました。ヘルスコミュニケーションの確立期から現在にかけて、実際に、学習・研究・実践への応用をしてきたからこそ、ヘルスコミュニケーションを明日からの実践に即役立つ講演やコンサルティングを提供することができます。
ヘルスコミュケーションのスキルを高め、人の健康に寄与したいのなら、患者や住民のことを想う気持ちが通じなくて残念な状況に陥りたくないのなら、一度弊社にお問い合わせください。
- 宮崎県串間市.胃がんバス検診受診率向上キャンペーンの結果、検診受診者数が1年間で5割以上、2年目には2倍に増加。詳細は下記文献をご参照ください。
文献:
蝦名&川崎(2011). 胃がんバス検診受診率向上キャンペーン~ヘルスコミュニケーション・ウィールを もとにした取り組み~.エビデンスの最前線&ナラティブな実践事例8.公衆衛生情報41, 5, 40-43. - 平成21~23年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業. 「生活習慣病対策における 行動変容を効果的に促す食生活支援の手法に関する研究」のうち 質的研究におけるアドバイス。
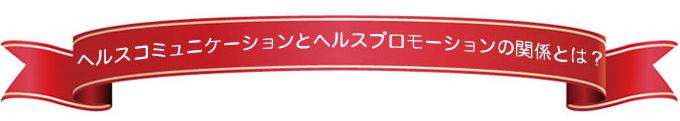
米国のヘルスプロモーション政策『Healthy People 2010』では,
効果的なヘルスコミュニケーションの際に検討すべき項目として以下の項目をあげています。
◆内容の正確性 ◆利用可能性 ◆メリット・デメリットのバランス ◆一貫性
◆文化的に受け入れられるもの ◆科学的な根拠 ◆対象とする人々のうち最高人数に届いているか
◆内容の信頼性 ◆繰り返し ◆良いタイミング ◆理解しやすさ
米国では、実際に、心理学や行動科学の理論を基に、ヘルスコミュニケーション戦略を練り、その際、これらの項目ができているかを確認することが、評価基準として、政策のなかであがられているわけです。
だから、こちらが伝えたいメッセージが伝わらないがために大した活動効果が得られなかった、
という結果を避けることができるのです。
蝦名(保健学博士)は、帰国後、わが国において「保健事業を実施したものの、
うまくそのメッセージが伝わらないがために成果が得られない」という多くの事例を見てきました。
このため「この状況はすごくもったいないことだ、何とか改善できるように貢献したい」と願う気持ちを高めています。
ヘルスコミュニケーションを、きちんと取り入れさえすれば、こういった問題は解決されます。
そして、弊社には、ヘルスコミュニケーションをきちんと取り入れるために必要な知識や経験、ノウハウがあります。
どんどん皆さまと共有して、創造的なアプローチ方法を一緒につくり
ヘルスコミュニケーションを広めていくことが、私たちの夢です。